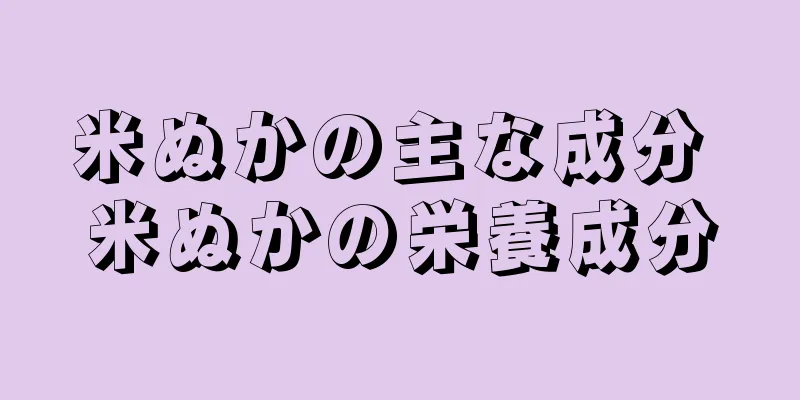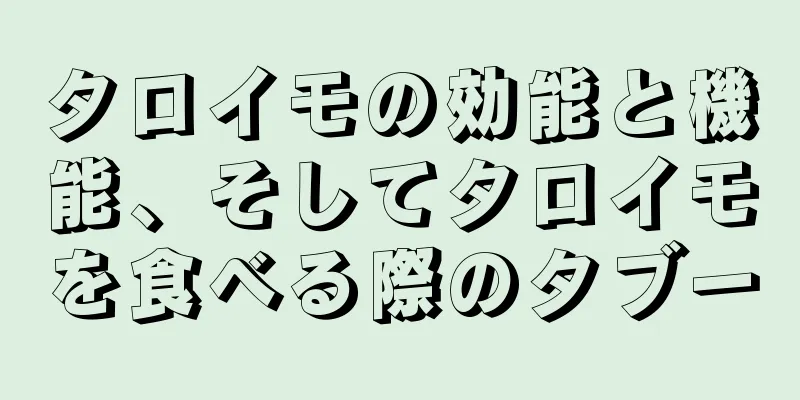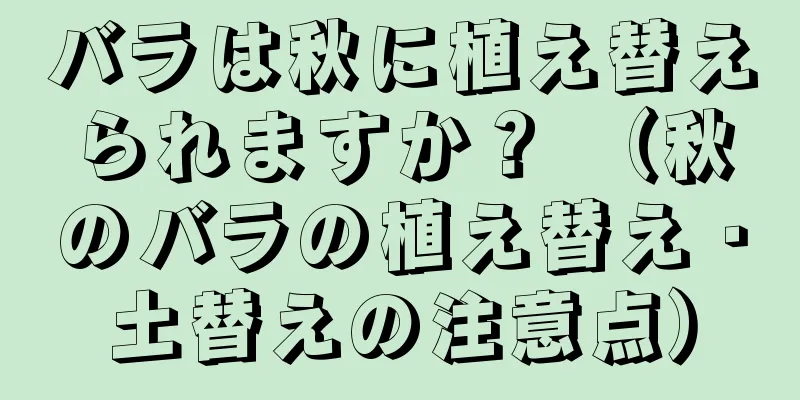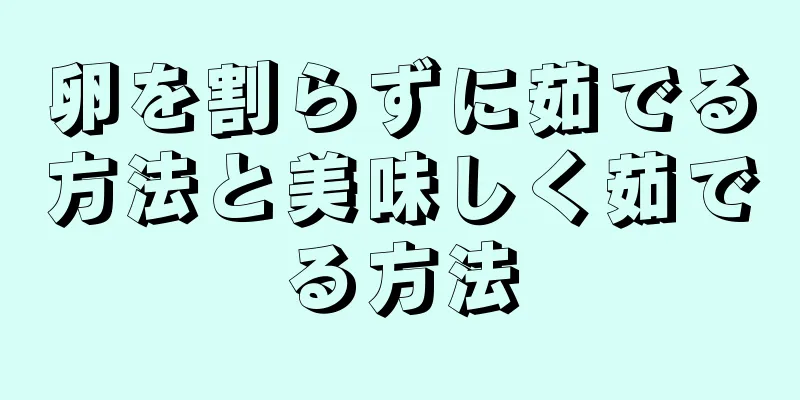クレロデンドルム・トムソニアエの剪定方法
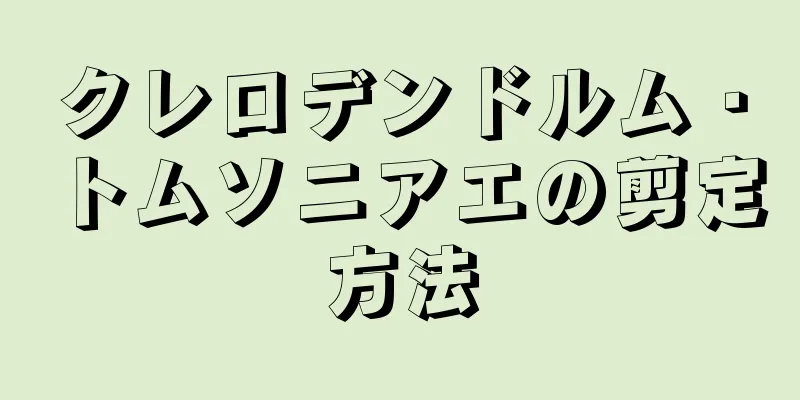
クレロデンドルムの剪定時期Clerodendrum thomsoniae は、登る能力のある小さな低木です。観賞価値を高め、栄養分の損失を減らすためには、頻繁に剪定する必要があります。 Clerodendrum thomsoniae は、毎年開花期後の 5 月から 6 月にかけて剪定できます。これは植物が旺盛に成長する時期であり、剪定後すぐに成長を再開することができます。 クレロデンドラム・トムソニアエの剪定方法1. トッピングとつまみ 種まきでも挿し木でも、苗の高さが15cmを超えると、植物の上部にある枝や葉を摘み取る必要があります。摘芯の目的は、植物の側枝の成長を促進し、植物の高さを制御することです。 2. 枝の剪定 また、クレロデンドラム・トムソニアエの成長過程では、黄色くなった枝葉や生い茂った枝葉、病気の枝葉を速やかに切り取り、開花期後に枯れた花を刈り込むことも必要です。これにより、栄養素の過剰な消費が減り、植物の成長が促進され、植物の観賞価値が向上します。 3. 枝を梳く Clerodendrum thomsoniae のメンテナンス中に、枝が密集して重なり合っているのを見つけた場合は、適時に間引き、密集しすぎた枝を切り落として、植物の光透過率を高める必要があります。そうしないと、植物の鑑賞に悪影響を与えるだけでなく、正常な成長にも影響を及ぼします。 4. 植え替えと剪定 クレロデンドラム・トムソニアエの成長速度は比較的速く、一般的には1~2年ごとに鉢の土を交換する必要があります。植物を植え替える過程で、腐った根や生い茂った根を切り取って、植物の成長を確実にすることができます。 5. 切断後の処理 Clerodendrum thomsoniae の剪定が完了したら、植物の管理を強化する必要があります。まず、切り口が細菌に感染するのを防ぐために植物を消毒します。日々のメンテナンスでは、光、水、栄養素を管理する必要があります。最も重要なことは、植物の迅速な回復を確実にすることです。 |
推薦する
キャッサバの調理方法 キャッサバを最高に調理する方法
キャッサバは、アメリカの熱帯地域に自生するユニークな植物です。独特の塊茎を持つ直立した低木です。その...
キンモクセイの土替え時期と方法
キンモクセイの土替え時期キンモクセイの土替えに最適な時期は、毎年10月から翌年の3月中旬までです。こ...
胃の調子が悪いときにはどんな果物を食べたらいいでしょうか?
人生において慢性的な胃腸疾患に悩まされ、多くの食事上のタブーを抱えている人はたくさんいます。最近、「...
木はいつ芽を出し、葉を生やすのでしょうか?
木の芽吹きの時期木には多くの種類があり、ほとんどの木は2月から3月に芽を出しますが、地域によって木の...
イチョウ栽培の注意点
イチョウの木は薬効のある植物です。イチョウの木はとても貴重です。イチョウの木を植えるには、基本的な方...
栗きび粥の効能と作り方
栗きび粥は日常生活でよく食べられます。朝食にも夕食にも食べられます。この粥は味が良いだけでなく、栄養...
カリフラワーの効能と機能、そしてカリフラワー摂取のタブー
カリフラワーは、カリフラワーとも呼ばれ、アブラナ科の植物の一種で、人々の生活の中で最も一般的に食べら...
ナツメケーキの作り方 ナツメケーキを美味しく作る方法
デーツケーキを食べたことがある人は多いでしょう。デーツケーキはデーツの風味が強いペストリーの一種です...
産前産後にネギのみじん切りを食べるとどんな効果があるのでしょうか?
産後、玉ねぎは食べるのに適していますか?一般の人が玉ねぎを食べることは問題ありませんが、妊婦、特に出...
青リンゴを水で煮ることの利点は何ですか? 青リンゴを水で煮ることの利点と機能は何ですか?
青リンゴは、シャキッとした食感と少し酸味のある果物です。リンゴ科の重要なメンバーですが、人々がよく目...
乾燥ショウガの効能と機能
千切り干し生姜は、生姜を洗って薄く切り、乾燥させたり焼いたりして作られ、調味料としてだけでなく、優れ...
自宅で蓮を育てることはできますか?
自宅で蓮を育てることはできますか?蓮は自宅で植えることができます。一般的には、家に大きな鉢を置いて、...
クレマチスに最適な土壌は何ですか?
クレマチスの土壌は、その根の成長を反映することができます。クレマチスの根がよく育つと、土の表面の草本...
桑の芽の効能と機能
桑の芽は桑の木の若芽です。毎年春になると桑の木は新鮮な若芽を成長させ、人々はそれを集めて冷凍保存しま...
ウキクサの写真とその効能と薬効
ウキクサは、黄金蓮、またはウキクサ蓮とも呼ばれ、スイレン科の植物の一種です。主に初夏に美しく優雅な花...