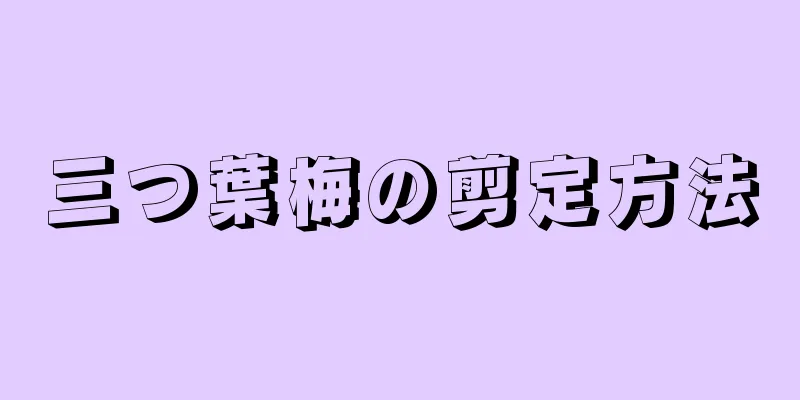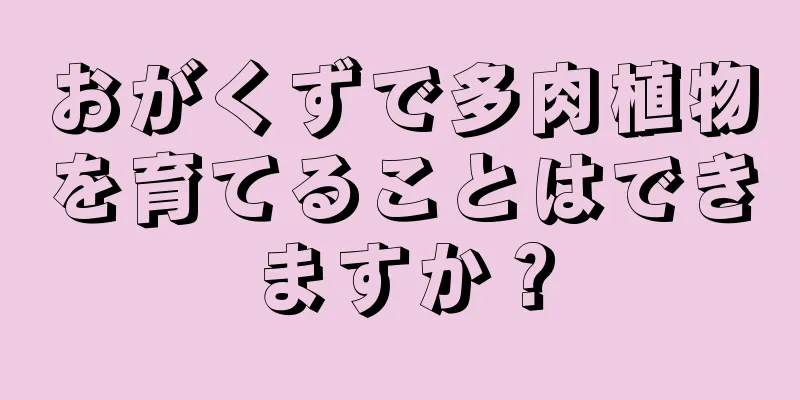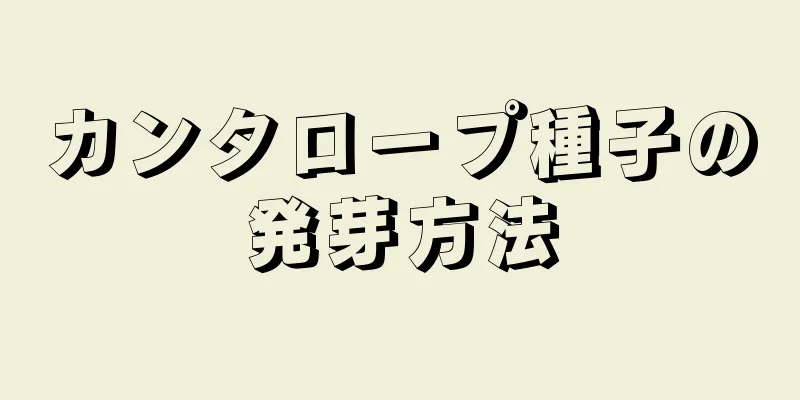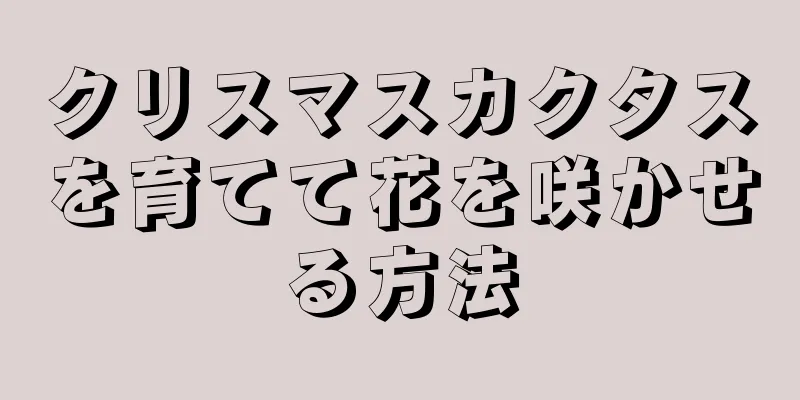ササゲの乾燥技術

|
実際、乾燥したササゲを食べるのが好きな人はたくさんいますが、どうやって作るのでしょうか? 具体的な手順は次のとおりです。 1. 材料の選択:虫害、さび、変形、損傷、汚染のない若いササゲを選んでください。乾燥した製品の長さや色が異なってしまうのを避けるために、異なる種類のササゲを別々に乾燥させるのが最善です。 2. ブランチング:若いササゲは繊細な食感なので、沸騰したお湯で茹でる時間は長くしすぎないようにしてください。一般的には、2~4分後に沸騰したお湯から取り出し、すぐに冷水に浸して余熱の影響が続くのを防ぎます。これにより、ササゲから出る粘着性物質も除去できます。 3. 色の保護:ササゲを湯通しする水に 0.5% の重曹を加えると、ササゲの緑色を保ち、乾燥したササゲの見た目の品質を向上させることができます。 4. 硫黄燻蒸:湯通ししたササゲを室内の竹マットの上に広げ、1立方メートルあたり200グラムの硫黄で燻製します。これにより、乾燥中の酸化、変色、腐敗を防ぎ、ビタミンCの損失を減らし、乾燥速度を促進し、完成品の水分補給特性が向上します。 5. 乾燥:自然乾燥は天候に左右されることが多いので、人工乾燥が最適です。大量生産用に独自のベーキングルームを設計することもできます。 6. 保管:乾燥したササゲを保存するときは、湿気や劣化を防ぐことに注意する必要があります。ポリエチレン農業用フィルムを使用して、大きな包装袋に溶接することができます。1袋あたり約20キログラムを収容できます。梱包後、袋を縛って密封します。このようにして、2年間は劣化しません。正式な商品として生産される場合は、包装を考慮する必要があり、きちんと包装できるように乾燥中にササゲを等級分けして形を整える必要があります。 |
>>: おいしいササゲの作り方は?卵風味のササゲの調理手順の詳細
推薦する
ブリティッシュリズムローズの長所と短所
ブリティッシュビートローズは他のバラとは全く異なります。このバラの花びらは一般的に鋸歯状になっており...
カーネーションの効能とタブー
カーネーションは母の花としても知られ、美しい観賞用植物です。真の愛情と優しい愛を象徴します。母親に贈...
冬瓜、蓮米、緑豆粥の材料と作り方
冬瓜、蓮米、緑豆のお粥は野菜と穀物の栄養価を兼ね備えており、調理が簡単で風味豊かで美味しいです。冬瓜...
人工浮島によく使われる水草 人工浮島に適した浮草
植物は地域性が非常に強いため、地元の水生植物や両生類植物の選択にはより注意を払う必要があります。北で...
ガチョウの卵を食べるとどんなメリットがありますか?
ガチョウの卵は、私たちの日常生活で食べる卵食材の中で最も大きいものです。ガチョウの卵の大きさは、鶏卵...
グリーンキウイフルーツの食べ方 グリーンキウイフルーツの食べ方
グリーンキウイは栄養価の高い果物です。果肉は一般的に緑色で、ビタミンCを多く含んでいます。グリーンキ...
亀の糞を使って花に水をやる利点は何ですか?亀の糞水を肥料として花に水やりに使う
カメを使って花に水をやるメリットカメの水を使って花に水をやると水資源を節約でき、水中の残留塩素も蒸発...
妊婦はマンゴスチンを食べても大丈夫ですか?妊婦がマンゴスチンを食べるとどんなメリットがありますか?
マンゴスチンは果物の女王として知られています。主に中国南部の熱帯地域で生産されています。栄養価が高く...
干しナマコの食べ方 干しナマコの食べ方
ナマコは海産物の中でも最高峰で、栄養価が非常に高い健康食品です。しかし、生ナマコの賞味期限は非常に短...
ヘチマの種類は何ですか
ヘチマの優れた品種は何ですか? この知識は、田舎に住む友人にはよく知られているはずです。ヘチマヘチマ...
海宝菌の栽培と食べ方
海宝菌は、ハイバオとも呼ばれ、乳酸菌、酵母、酢酸菌の共生菌です。有機酸、糖、ビタミンB、C、レシチン...
ジャックフルーツは南部でも栽培できますか?
ジャックフルーツは南部でも栽培できますか?ジャックフルーツは、高温多湿の環境で育つことを好む熱帯果物...
紫牡丹の生育環境と地域条件
紫牡丹の生育環境と条件紫牡丹は主に中国の雲南省北西部、四川省南西部、チベット南東部に分布しています。...
白いヤシの花を鉢に分ける方法、いつ、どのように分けるか
白いヤシの花を鉢に分ける時期白いカラーリリーは、ダメージが最も少ない 5 月と 6 月に植え替えるの...
ザクロは体内を熱くしますか?ザクロは冷やすものでしょうか、それとも温めるものでしょうか?1 日に何個のザクロを食べるべきでしょうか?
ご存知のとおり、ザクロは甘くて栄養が豊富で、健康に優れた果物です。また、人生で人々が好む果物の 1 ...