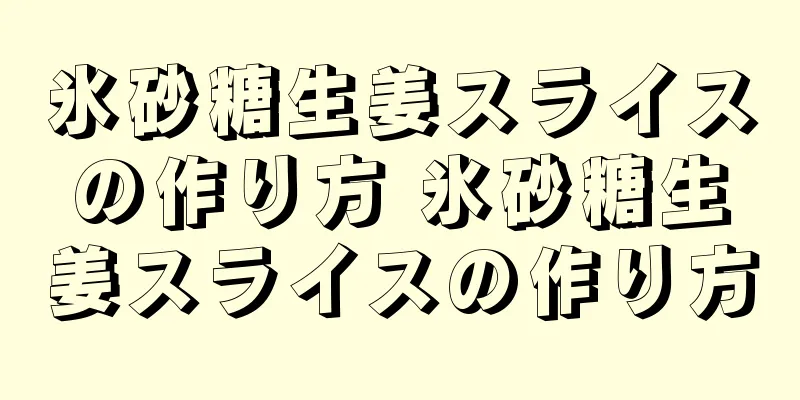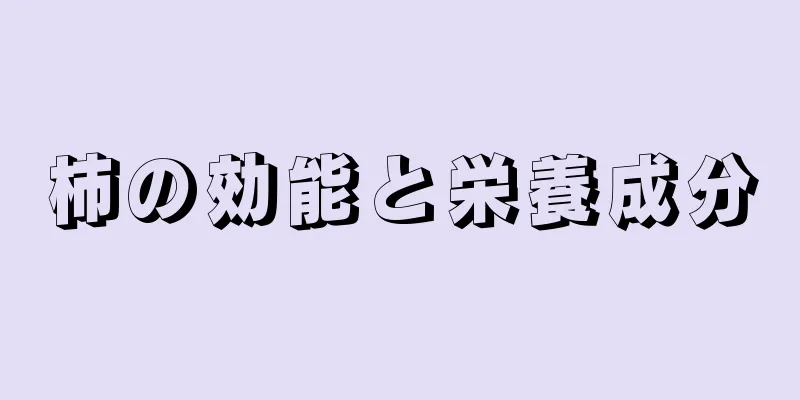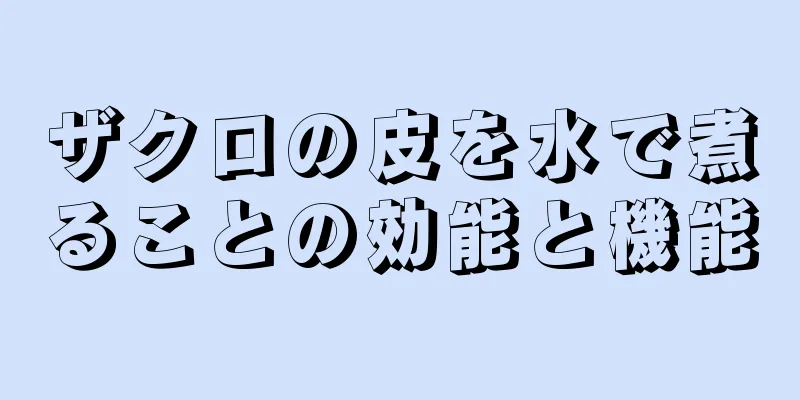お正月みかんの漬け方とお正月みかん蜂蜜の作り方
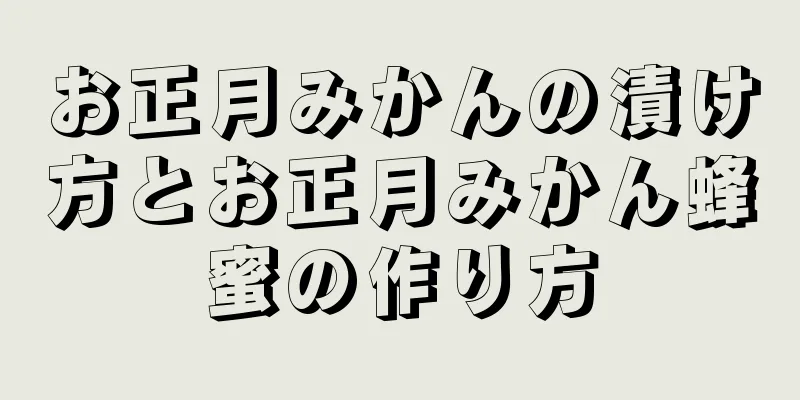
|
みかんはオレンジの木に実る果物で、ミカンの一種です。正月みかんは、春節の時期である1月から2月にかけて成熟し、市場に出回ります。正月みかんは栄養価が高く、意味も優れています。多くの人は、年末までに大量の正月みかんを用意して、新年を祝ったり、親戚や友人に贈ったりします。たくさん準備するので、お正月のみかんは年が明けても食べきれないかもしれません。そんなときは、みかんを漬けてみかん蜂蜜にすることができます。 新年のみかんの漬け方1. 傷んでいない、腐っていないみかんを選び、きれいな水で洗い、ふるいにかけて天日干しします。みかんの表面の水分が完全になくなるまで、1~2日乾燥させます。使用していないガラス瓶は洗って乾かし、滅菌器に入れて高温殺菌します。 2. ガラス瓶の底に塩を薄く振りかけ、洗ったオレンジをガラス瓶の中にきれいに並べます。オレンジの層ごとに塩を薄く振りかけます。オレンジをうまく漬け込み、より本格的な味にするために、もう少し塩を加えることもできます。ただし、塩を盲目的に加えすぎると、オレンジが苦くなる可能性があるため、注意してください。 3. 次に、蓋をします。微生物や細菌の侵入を防ぐために、できればしっかりと密閉してください。瓶にラベルを貼り、オレンジを漬けた日付を記入します。こうすることで漬けた時間を簡単に確認でき、いつ食べられるかがわかります。通常、約1か月後に開封して食べることができます。 みかん蜂蜜の漬け方お正月みかんは塩漬けにして塩みかんにしたり、砂糖や蜂蜜に漬けて蜂蜜みかんにしたりできます。作り方は実は似ています。オレンジを洗った後、用意した容器に入れます。各層に適量の砂糖または蜂蜜を振りかけます。甘いものが好きな場合は、砂糖や蜂蜜をさらに追加できます。そして密封して保存します。1ヶ月後には甘いお正月みかん蜂蜜が楽しめます。 |
<<: 乾燥した蓮の実の硬い殻の剥き方 乾燥した黒蓮の実の硬い殻の剥き方
>>: シーバックソーンワインの効果と効能、そしてシーバックソーンワインを飲むことの利点
推薦する
ダフネ・オドラに最適な土壌は何ですか?
キンモクセイは土壌に対する要求度が比較的高く、緩く通気性のある土壌を好みます。この植物は肉質の根を持...
枝豆を植えるのに最適な季節はいつですか?
枝豆の植え付け時期と時期枝豆は春と夏に植えることができます。夏は2月上旬から3月上旬に播種し、夏は4...
ニベの揚げ方
ニベの揚げ方は?以下に詳しく紹介させていただきます。ニベの揚げ物男性でも料理ができる?全然不思議じゃ...
モンステラの育て方 モンステラを育てる際の注意点とタブー
モンステラは美しい緑の葉を持つ植物で、特に室内栽培に適しています。室内の空気を浄化し、放射線に抵抗し...
パイナップルを食べるときに注意すべきことは何ですか?
パイナップルは私たちの日常生活でよく見かける果物です。表面にはトゲがあり、果肉は主に黄色です。甘酸っ...
ハニーグレープフルーツティーの健康効果とは
ハニーグレープフルーツティーは最も人気のある健康茶です。栄養価が高いだけでなく、健康効果も抜群です。...
シロガニとワタリガニの違い
シロガニとワタリガニの違いワタリガニ。一部の地域では「シロガニ」とも呼ばれています。頭と胸甲がシャト...
にんじん塩粥
実は、にんじん塩味775粥の作り方はにんじん粥と似ています。一緒にこの粥について学んでみましょう。に...
ピーナッツの殻を使って多肉植物を育てることはできますか?
ピーナッツの殻を使って多肉植物を育てることはできますか?ピーナッツの殻は多肉植物を育てるのに使うこと...
ジェイドリーフの増やし方と注意点
玉葉の繁殖方法セダムの繁殖方法は、播種繁殖、株分け繁殖、挿し繁殖、葉挿し繁殖の 4 つがあります。な...
レンギョウ盆栽の栽培方法
レンギョウは枝葉が茂り、傘のような形をした木です。レンギョウ盆栽はインテリアとしても最適です。ここで...
コーンミール粥の作り方 コーンミール粥の作り方
コーンミール粥はとても美味しいお粥です。多くの人がそれを食べたいのですが、どのように作られるかを知り...
アガベ・ギルテンドレの効能と機能
アガベ・ギルトエッジは多年生の常緑植物です。リュウゼツラン科の植物、アガベ・ゴールデンエッジディフォ...
アロエベラの食べ方 アロエベラの食べ方
アロエベラは多くの人が知っています。多くの女性の友人がアロエベラを美容ケアに使用し、フェイスマスクを...
赤ワイン漬けパパイヤの効果と働き 赤ワイン漬けパパイヤの3大効果
赤ワインに浸したパパイヤを食べたことがありますか?その効果と機能は何かご存知ですか?赤ワインに浸した...